はじめに:英語学習には文化と感覚が鍵
英語に限らず言語を勉強している人であれば
誰もがネイティブの感覚が欲しいと願うものではないでしょうか。
私もその一人。
毎日、私もネイティブの感覚を身につけるために必死です。
エッセイを書くにも、どうしても「日本人らしさ」が出てしまうのが悩みです。
なので、文章をたくさん書いて、書いて、書いて、考えて続けました。
そして、分かったこととは・・・
ネイティブの感覚を身につけるためには
文化と感覚のバランスが重要であるということです。
日本語と英語ネイティブの違い
日本語らしい文章の例

私は、これまで多くの英文のエッセーを書いてきて
私の英語の文章は日本語らしい文章の構成であると感じていました。
その理由は・・・
結論や主張が文章の最後に来てしまいがちであるためです。
少し例文を用いて紹介します。
- 私は苦い方が好きなので、コーヒーをよく飲みます。
- 私はコーヒーをよく飲みます。苦い方が好きなので。
日本語であれば、1.の文章の方が自然ですね。
しかし、英語にすると・・・
と訳すことができるかもしれません。
でも、この文章は文法的に正しくても、ネイティブらしい文章とは言えないでしょう。
ネイティブらしい文章は
と、becauseを使う文章です。
私がIDIYで英語の講師をしている時や、中学校で英語の教師をしている時
日本人の英語学習者の方々は、becauseよりもsoを好んで使う印象でした。
【元アイディー講師が解説】IDIYの効果的な使い方と英語学習のアドバイス
でも、その気持ちは十分に分かります。
日本語では・・
理由を述べてから結論を述べる傾向にありますから。
もちろん、プレゼンテーションの技術や話し方の本を読むと
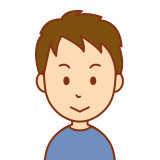
結論を先に述べると、伝わりやすい話し方ができますよ!
なんて、アドバイスが載っていたりしますが
実際の日本人同士の普段の会話では、結論が後回しになる傾向が強いと感じます。
その理由は、文化的な背景にも影響します。
日本の文化的な背景

日本の文化のもとでは、結論を先に述べなくても、
話の流れをある程度汲んで話の内容を聞き取ることが求められます。
それが、「空気を読む」であったり「調和を大切にする」であったり
言葉がなくても、日本人には
今、何をすべきなのか?
ということを共有できる文化が存在しています。
人類学的側面から考えると、それは日本が農耕民族であり
コミュニティーを大切に、相手と協力をしないと
主食となるお米を育てることができなかったということまで遡ることができるんです
(でも、今回はその説明は割愛します)
このように、日本文化では常に相手の気持ちやコミュニティーの意向を汲むことが重視されているので
結論は先に言わなくても、分かり合えるんです。
そのため・・・
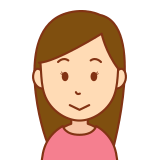
飲み物どれにする?
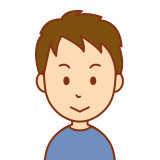
そうだな〜、僕、苦い系苦手だから・・・
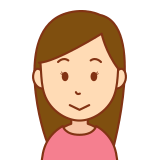
んじゃ、甘めのキャラメルマキアートなんてどう?
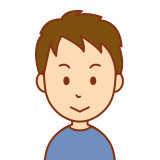
あ!いいかも!
なんていったように・・・
男の子が理由しか述べていないにも関わらず
女の子は、メニューから、男の子が飲みたいものを提案することができる様子が
日本人のあるあるな会話スタイルです。
英語圏の文化と話し方

上に示したような、カフェでの会話は
日本人であれば、普通の会話のように思えるかもしれません。
それは、私たちの文化と感覚が
上記のような会話を当たり前のようにさせているからでしょう。
でも、英語ネイティブの人の会話であれば・・
きっと・・・

What would you like to drink?

Well, I will order caramel macchiato because I am not good with a bitter taste.

Alright! Then, I will have the same one.
と、自分の意見を単刀直入に述べる様子が伺えると思います。
もちろん、会話の違いには
- 相手との関係性
- 人それぞれの性格
など、そのほかの要素も含まれますが
日本語のネイティブの私たちよりは、直接的な対話を好むでしょう。
それは、文化的な背景に基づいていると言えます。
文化と感覚を習得するためには?

日本語と英語の言葉の違いと、日本文化と海外の文化の違いが少し分かったところで
一番気になるところは・・
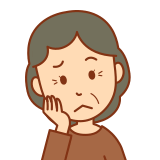
どうすれば、ネイティブのようになるために、彼らの文化を習得して、彼らのような感覚を身に付けられるの?
という点だと思います。
それでは、この疑問に対して、西洋文化らしく結論から述べたいと思います。
それは、時間のかかることですが
- 常にネイティブの言葉の使い方や文章の書き方に目と耳を向け
- 彼らの使った言葉と状況を自分の感覚に刷り込んでいく
このような点を意識して勉強する必要があります。
小難しい言葉を並べてしまいましたが・・・
私が実際に遭遇した例をあげたいと思います。
文化と感覚を意識した私の体験

私は、イギリスに行って、Lovelyという言葉を毎日のように耳にしました。
それまで、Lovelyという言葉は

ワンちゃん・ねこちゃんがかわいい〜♪
という時くらいしか、lovelyなんて使いませんでした。
でも、イギリス人は
- とても天気がいい!= Lovely
- このご飯美味しい!=Lovely
- プレゼントもらって嬉しい!=Lovely
と表現します。
私は、イギリス人がLovelyを発した瞬間の状況を見て、「今がLovelyね!」
と、彼らの感覚と状況を目で見て、耳で聞いて、刷り込んでいく体験を積み重ねていきました。
つまり、彼らのLovely文化を習得すために
彼らを観察し、状況を見て、実際に自分の感覚に刷り込んでいくように心がけたんです。
しかし、残念ながら、私はなかなかLovelyを使うことができません。
私にとって・・・
いい天気なら、Nice weatherだし、美味しいなら、taste good だし、嬉しかったら、wow, thank youだし・・・(笑)
なので、感覚と文化を習得するには
時間をかけて、英語のネイティブスピーカーの側にいて学んでいく必要があるんだろうな〜と感じています。
そうすることで、日本語らしい英語から、ネイティブらしい英語の使い方に変わっていくはずです。
(時間はかかりますが・・・)
終わりに:日本国内でも文化と感覚は異なるもの

本日2020年9月23日水曜日。
私は、京都にいます。
今回の記事を書こうと思ったのは、今朝の出来事がきっかけです。
私は、妹の洋服を取りにクリーニング屋さんへ行きました。
洋服を受け取り
私が、「ありがとうございます。」
と言ったら、クリーニング屋のおじさんは
「ありがとう。おおきに。」
と言ってくれました。
私はこの瞬間
「あ・・・私の日常生活の中で初めて「おおきに」を言われた。」
「おおきにって、今使うんだ!」
と分かった瞬間でした。
私は、「おおきに」という言葉は知っているのものの
東北出身のため生活の中で、これまで耳にすることは一切なく、とても新鮮でした。
それと共に・・・
ふと思ったことは
「おおきに」とは、単に「ありがとう」という方言なのか
それとも・・・
- 「おおきに」には、「ありがとう」では伝えきれない意味が含まれているのだろうか?
- 京都の人は、「おおきに」と「ありがとう」をどのように使い分けているのだろうか?
ということ。
この答えは、私には分からないです。
その理由は・・・
私は京都の言葉のネイティブでもなければ、生まれた文化圏も違い、そのネイティブ感覚を持っていないので・・・。
終わり!
\異文化の魔法サポーター募集中/
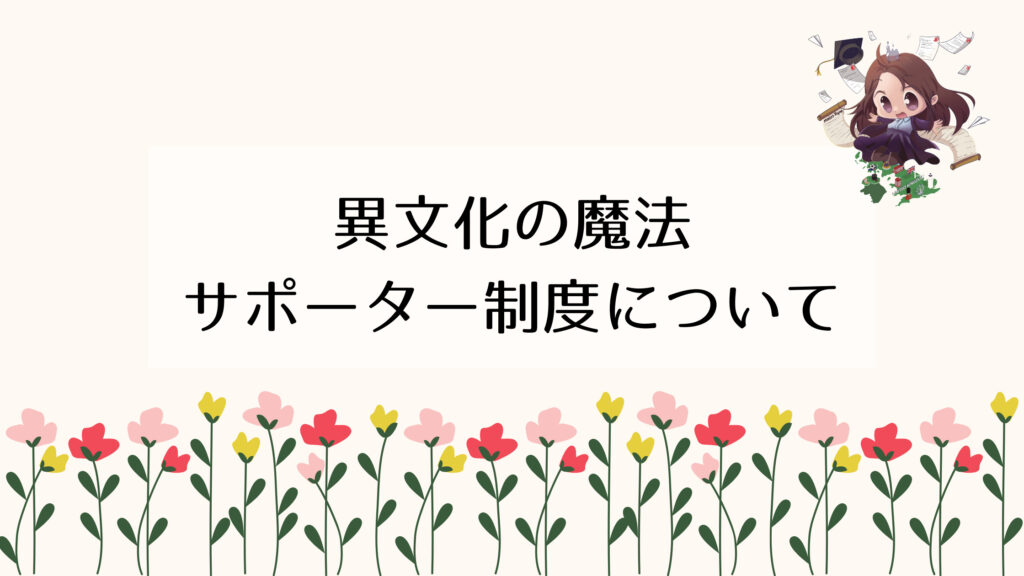
読者の皆様へ
異文化の魔法の記事がお役に立ちましたら、異文化の魔法サポーターという形でブログを支援してみませんか?
異文化の魔法の運営を始めてから、当ブログはどんどんと知名度が上がり、お問い合わせやTwitterのDMから色々なご質問が寄せられ、そちらにお返事をする機会も多くなってきました。
しかし、本サイトでの情報発信を継続させるためには多少なりとも運営費が発生しております。
異文化の魔法の運営は私たちの楽しみである一方で
ブログ運営のために情報収集を行い、記事としてまとめる作業や、お一人お一人に、お返事を書く作業は、かなりの時間を費やしているのも事実です。
それでも、やはり多くの方々に目標を達成してほしいという願いは変わりませんので、学業の側、この異文化の魔法を少しでも長く運営させようと努力はしております。
そんな私たちの思いを応援してくださり、異文化の魔法の運営継続を願い、このブログをご支援をしたいと思ってくださる方がいらっしゃいましたら、ぜひ、一度、異文化の魔法サポーター制度のご利用をご検討いただければと思っております。
サポートの詳細は、下記の三通りの方法があります
1.Amazonギフトカードを送る
2. noteで支援する
3. Amazonの欲しいものリストから干し芋かチョコを送る
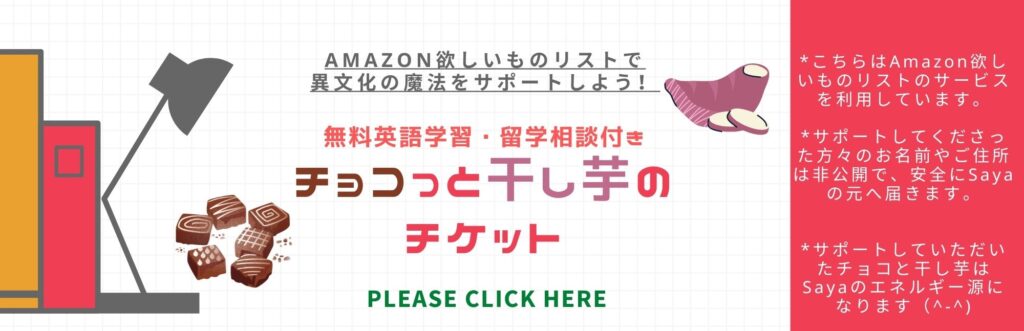
異文化の魔法サポーター制度の詳細につきましては、下記の記事をご覧ください
ぜひ、異文化の魔法サポーターとしてのご支援をよろしくお願いいたします。

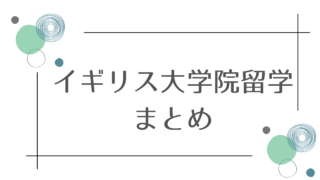
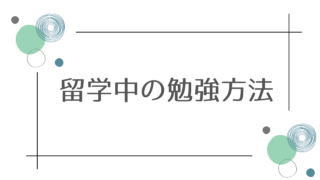
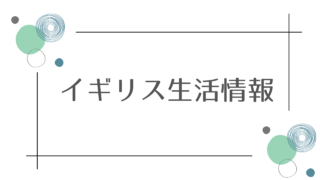
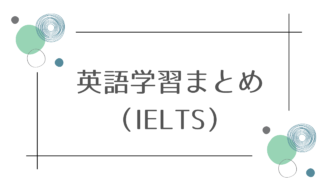




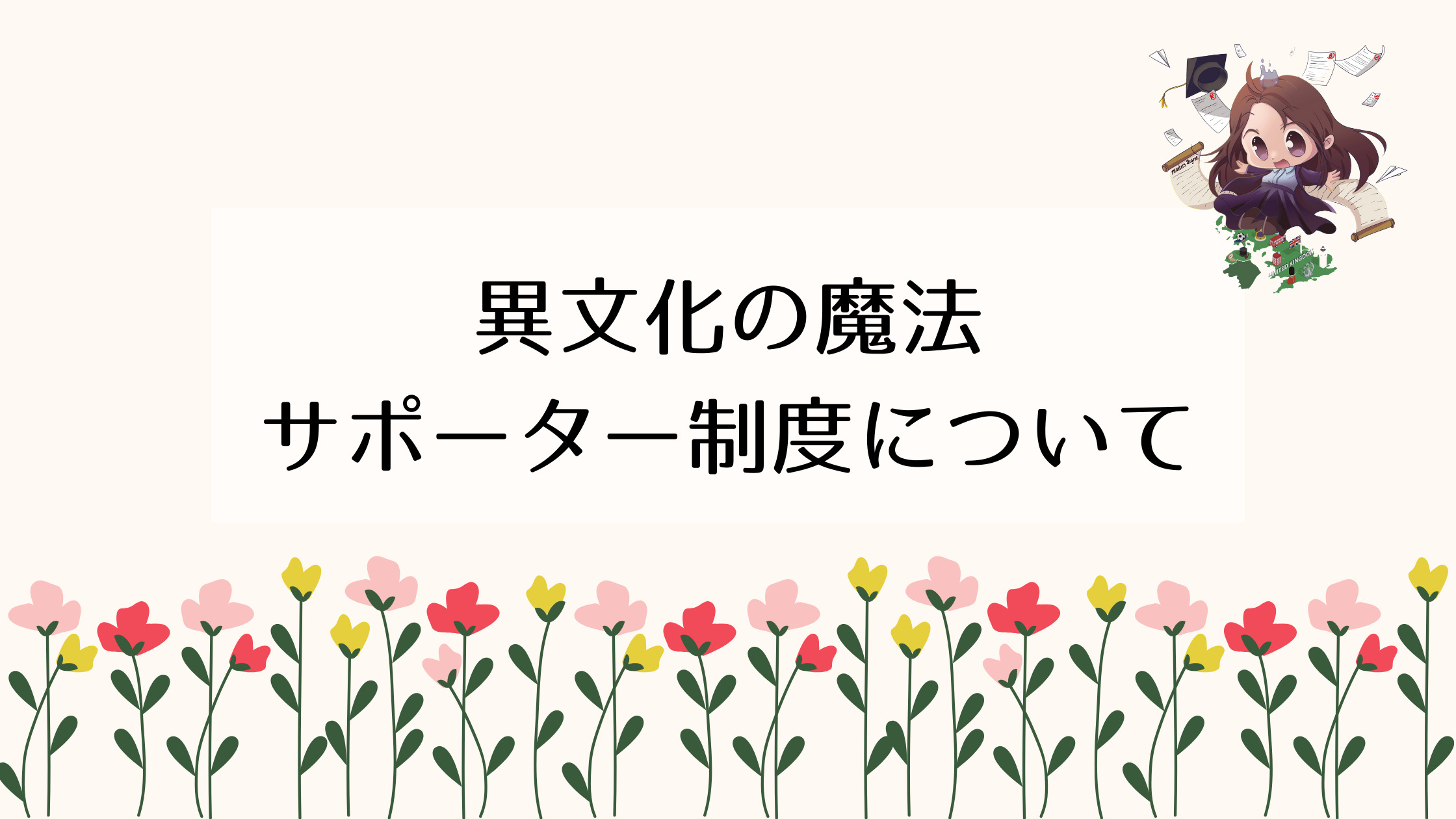
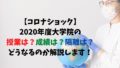

コメント