はじめに:エッセイを書くステップ
こんにちは!Sayaです。
今回は、エッセイの書き方のコツとしてピアレビューの重要性についてお話していきます。
エッセイのコツのシリーズとして
以前には、海外留学で覚えたい文献管理方法についてご紹介しました。
文献管理はエッセイの基本ですから、ぜひそちらの記事もご覧ください。
早速ではありますが、私はエッセイを書くステップを
大きく三段階のプロセスがあると考えています。
- 自分自身と向き合うステップ
- 読み手と向き合うステップ
- 読み手と自分自身の考えと向き合うステップ
とても抽象的な3ステップですが、今回はそれぞれのステップについて解説しつつ
ピアレビューがどれだけ重要であるか!
という点を述べていきたいと思います。
ステップ1:自分自身と向き合う


エッセイを書く作業とは自分との戦いである。
これは、私が常に思っていることです。
このエッセイとは、大学院留学先で提出するレポートだけではなく
- Personal Statement の作成をするとき
- 【留学準備書類】Personal Statementに何を書くか?
- 奨学金の申請書の作成をするとき
- 奨学金の志望動機書に書くべき3つのポイント
などにおいても考えるべきことです。
- エッセイに書くべき答えを知っているのは自分
- 情報を選択するのも自分
- 区切りを決めるのも自分
- 満足するのも自分
つまり、書く作業とは自分自身と向き合うことそのものだと考えます。
しかし、自分自身のことなのに、自分を理解し相手に伝える作業って本当に難しいんです。
また、エッセイを書く際には
- 自分はこのエッセイで何について述べたくて
- 読み手に何を知って欲しくて
- 何をまとめとするのか?
ということを明確に記さなければいけません。
もちろん、書き手自身が、書き綴りたい理論を正しく理解していなければ
上手なエッセイは書けませんので

私は何を理解していて、何を理解していないのか?
ということを、考えながらエッセイを書く必要があるんです
が!!

それを分析することも難しい(苦笑)
そんな自分と向き合うループを繰り返すことが、良いエッセイを書くコツの一つですので
エッセイは自分との戦いであると私は考えます。
- 自分はこのエッセイで何について述べたくて
- 読み手に何を知って欲しくて
- 何をまとめとするのか?
- 現状で何を理解していて、何を理解していないのか?
ステップ2:良いエッセイを書くには「読み手」と向き合う
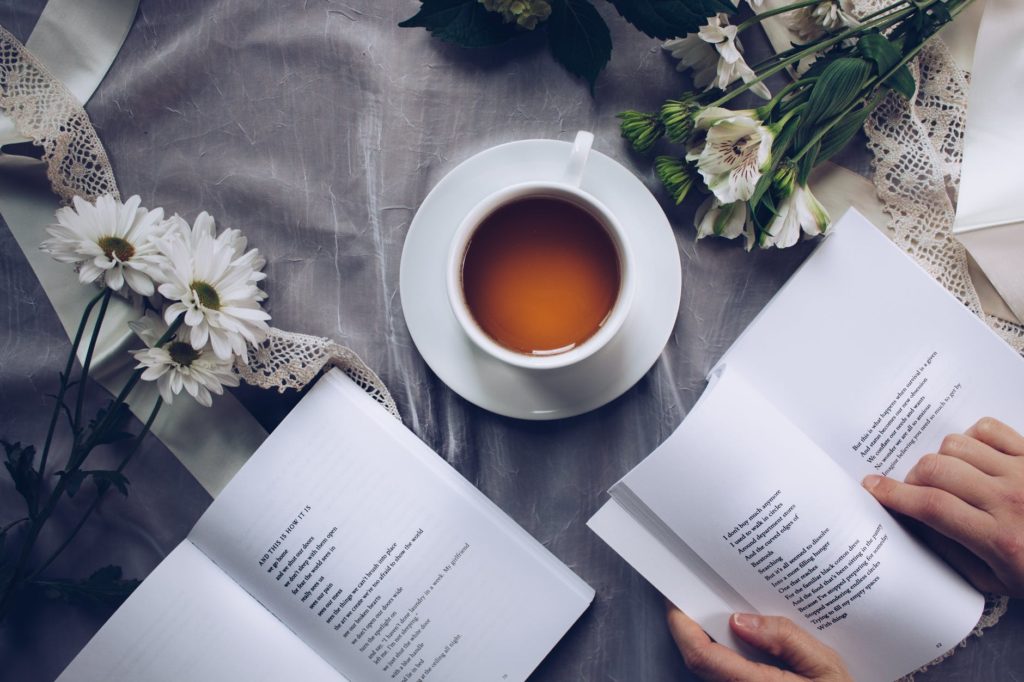
さて、書くことは自分との戦いであると述べましたが
エッセイの面白いところとは(厳しいところ)
評価を下すのは「読み手」であることだと思います。
- 深い自己分析をしても
- 自分なりに詳しい説明が書けたとしても
- 自分が伝えたい主張を盛り込めたと自信があったとしても
読み手の一存で良し悪しが決まるんです。
なので、よく出来たPersonal Statement や奨学金の申請書も
当然ですが、読み手が良くないと思えば、落ちます。
もちろん、エッセイだっていい評価は貰えません。
なので、文章を書く際は、ある程度のところまでは自分と向き合い
その後、誰かに意見を求めることが重要なのです。
一般的に、書く行為には締め切りなどの期限があると思うので

その期限を考えながら、頃合いを見て誰かに時間を作ってもらうことをおすすめします。
つまり、この誰かに読んでもらって意見をいただくプロセスのことを
私は「読み手と向き合うステップ」と呼んでいるのです。
そして、この読んでもらうプロセスが今回の記事のテーマであるピアレビューなんです。
- 評価者は他者であることを忘れない
- 自分一人では「良い文章」は完成させられない
- 誰でも論点が分かる文章を書くためには、必ず誰かにチェックを入れてもらわなければ、気づけないものである
ピアレビューの重要性
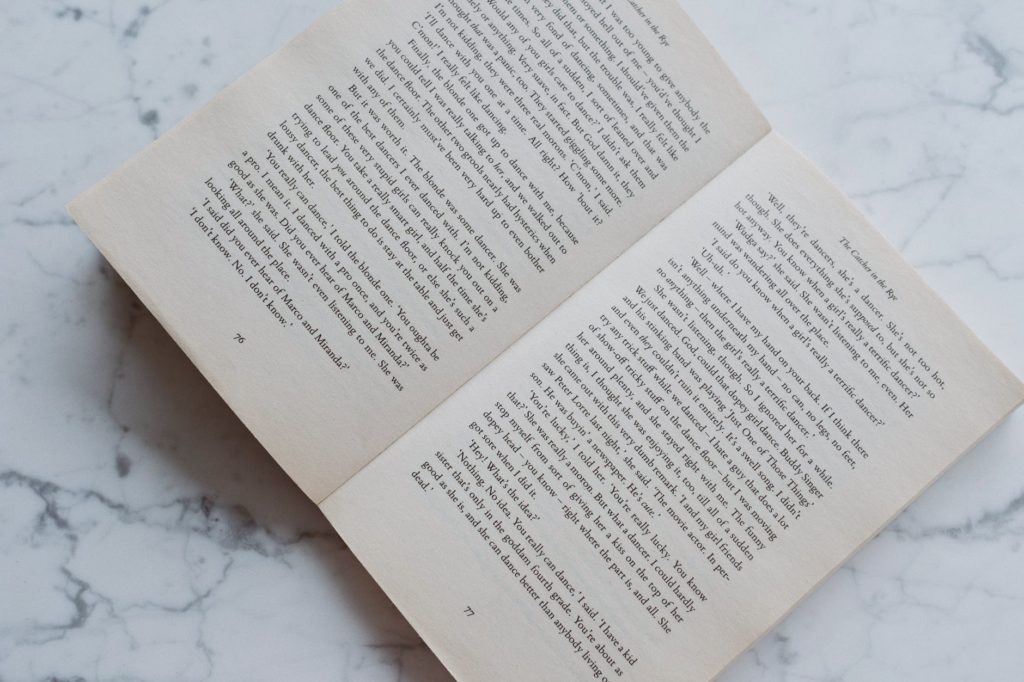
良いエッセイを書くためには他者が重要であるということを念頭におくと
ピアレビューは良いエッセイには欠かせません。
なので、もし同じコースに仲の良い友達がいれば
友達と一緒にピアレビューをしてみてください。
ピアレビュー(Peer Review)とは?
お互いのエッセイを読み合って、アドバイスをする活動のことを示します。
ピアレビューのやり方

ピアレビューの相手は、自分のコースとは全く違うコースの人でもOKです。
むしろ、そっちの方がいいかもしれません。
自分の学んでいることの基礎を知らない人でも
自分が書いたエッセイを読んで、内容が理解できるということはかなり完成度の高いエッセイですからね!
しかし、ピアレビューは結構気を使うものです。
自分が読み手になった時に、相手の言いたい主張が読み取れず

ここが分からないよー
と思った時には、率直に「ここが分からない」と伝えるだけでは
相手への思いやりに欠ける感じがするからです。
毎日文献をたくさん読んで、時間をかけて作成したエッセイに対して
たった一言
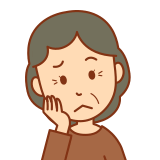
ここが分からない
なんて言われた時の落ち込み方は、ひどいものです。
なので、ピアレビューをする時には必ず

ここの部分をこんな展開で書いてみたら分かりやすくなると思う

ここに定義を入れたら、その分野を知らない私でも理解が深まると思う
のように、自分が文章を書くとしたら、どんな工夫をするか?
と、読み手として感じた文章の違和感を
書き手の立場になった時に、どのように改善するか?
といった視点で伝えるようにするといいです。
そうすると、相手からも有益なアドバイスをもらえるはずですよ。
ステップ3:自分と相手と向き合ってみる
さて、ピアレビューで読み手の意見をもらったあとは
読み手と自分の考えをすり合わせる最後の工程に入ります。
その際に一番大切にすべきことは
ピアレビューで頂いたアドバイスは素直に受け止めることです。
おそらく、ピアレビューをすると、時にはこんな気持ちになることもあるかもしれません。

あれだけ長い時間考えて、5000wordsものエッセイを書き上げたのに、ピアレビューの意見を取り入れたら、構成が大きく変わってしまう・・・。
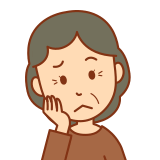
私の理論の理解が甘かったみたい。今から全て書き直しなんかできないわ。
きっと、これはあるあるです。
しかし、読み手に頂いたコメントこそが自分自身のエッセイの質を高めるためのヒントであることは忘れてはいけません。
長い時間をかけて書いた文章の方向性が変わってしまうことは切ないことなのですが
なるべく、読み手の意見を素直に受け入れて、文章を再構築する努力をしてみましょう。
もちろん、大きく構成が変わってしまうこともありますし
期限の関係上、全てを変更することはできませんので
情報の取捨選択が必要になってきます。
なので、改めて自分と向き合う際に
読み手のアドバイスの中で、どの部分なら改善できるのか?
という点を考えてみるといいと思います。
期限のギリギリまで、読み手の意見を含めてエッセイの改善をはかり
自分の最大限の力を発揮してみましょう。
エッセイには100%の答えというものがありませんので
最低限、できる限りの努力をすることしか、エッセイの質を高めることはできません。
あとは、天のみぞ知る(というか、採点者次第)です。
終わりに:ピアレビューをするもしないもあなた次第
イギリスの大学院は1年間という非常に短いコースなので
課題の締め切りまでの時間も短いです。
そのため、実際のところ今回提案した3ステップのうち
ステップ1のみでエッセイを提出してしまう人はたくさんいます。
- 自分自身と向き合うステップ
- 読み手と向き合うステップ
- 読み手と自分自身の考えと向き合うステップ
また、ピアレビューで意見をもらっても、書き直しができず
結局は、ピアレビューをうまく活用できない学生さんが多かったりもします。
でも、そこが成績や合否の差になるんだと感じます。
また、この差はタイムマネージメント力の差とも大きくつながっている気がします。
ですから、ピアレビューの時間と、その意見を反映させるための訂正の時間を含めて
エッセイ作成の時間配分を考えてみるのをおすすめしますが・・・・
ピアレビューはやらずともエッセイを完成させることができますので
結局、エッセイとは自分との戦いだと私は感じるのです。
\異文化の魔法サポーター募集中/
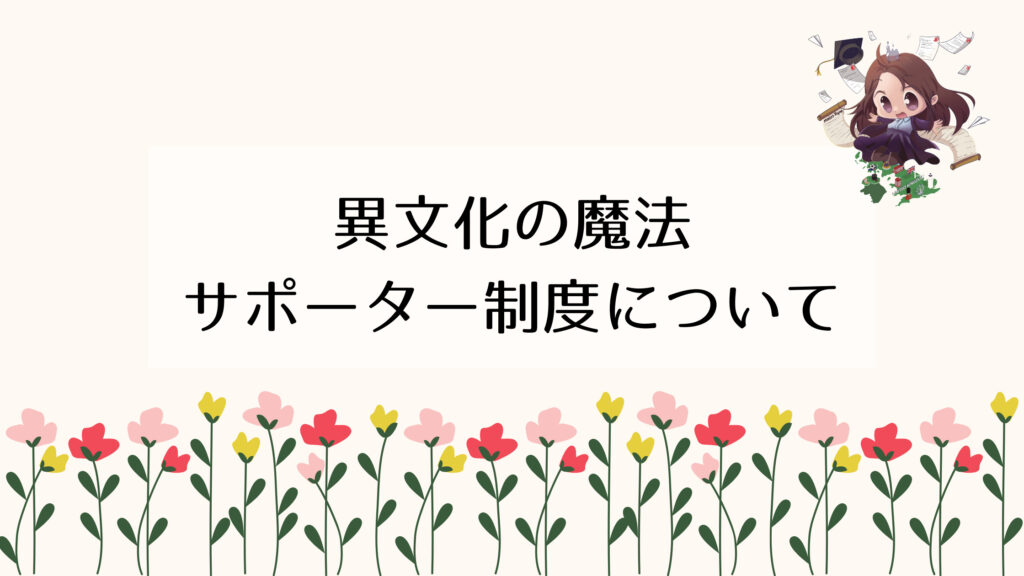
読者の皆様へ
異文化の魔法の記事がお役に立ちましたら、異文化の魔法サポーターという形でブログを支援してみませんか?
異文化の魔法の運営を始めてから、当ブログはどんどんと知名度が上がり、お問い合わせやTwitterのDMから色々なご質問が寄せられ、そちらにお返事をする機会も多くなってきました。
しかし、本サイトでの情報発信を継続させるためには多少なりとも運営費が発生しております。
異文化の魔法の運営は私たちの楽しみである一方で
ブログ運営のために情報収集を行い、記事としてまとめる作業や、お一人お一人に、お返事を書く作業は、かなりの時間を費やしているのも事実です。
それでも、やはり多くの方々に目標を達成してほしいという願いは変わりませんので、学業の側、この異文化の魔法を少しでも長く運営させようと努力はしております。
そんな私たちの思いを応援してくださり、異文化の魔法の運営継続を願い、このブログをご支援をしたいと思ってくださる方がいらっしゃいましたら、ぜひ、一度、異文化の魔法サポーター制度のご利用をご検討いただければと思っております。
サポートの詳細は、下記の3通りの方法があります
1.Amazonギフトカードを送る
2. noteで支援する
以下の記事のご購入も支援につながります!
3. Amazonの欲しいものリストから干し芋かチョコを送る
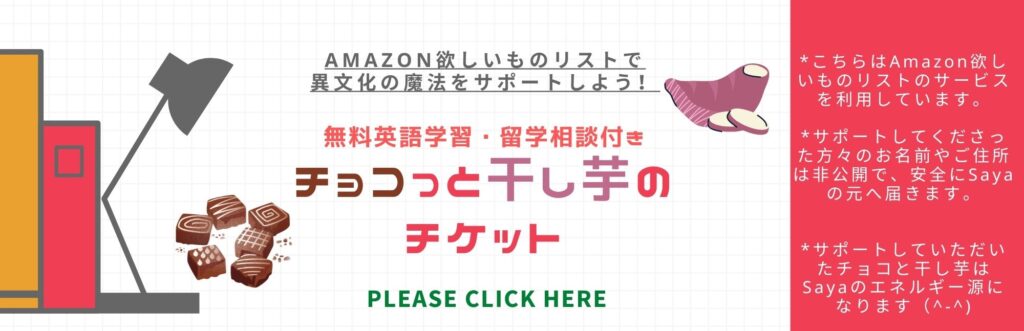

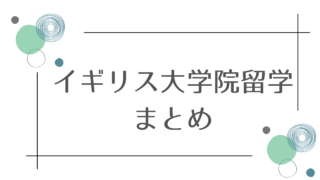
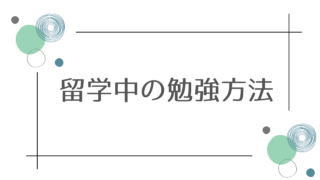
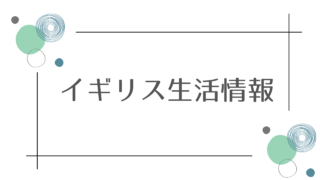
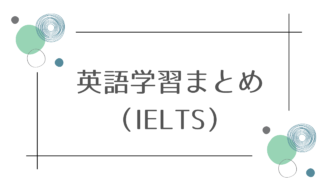


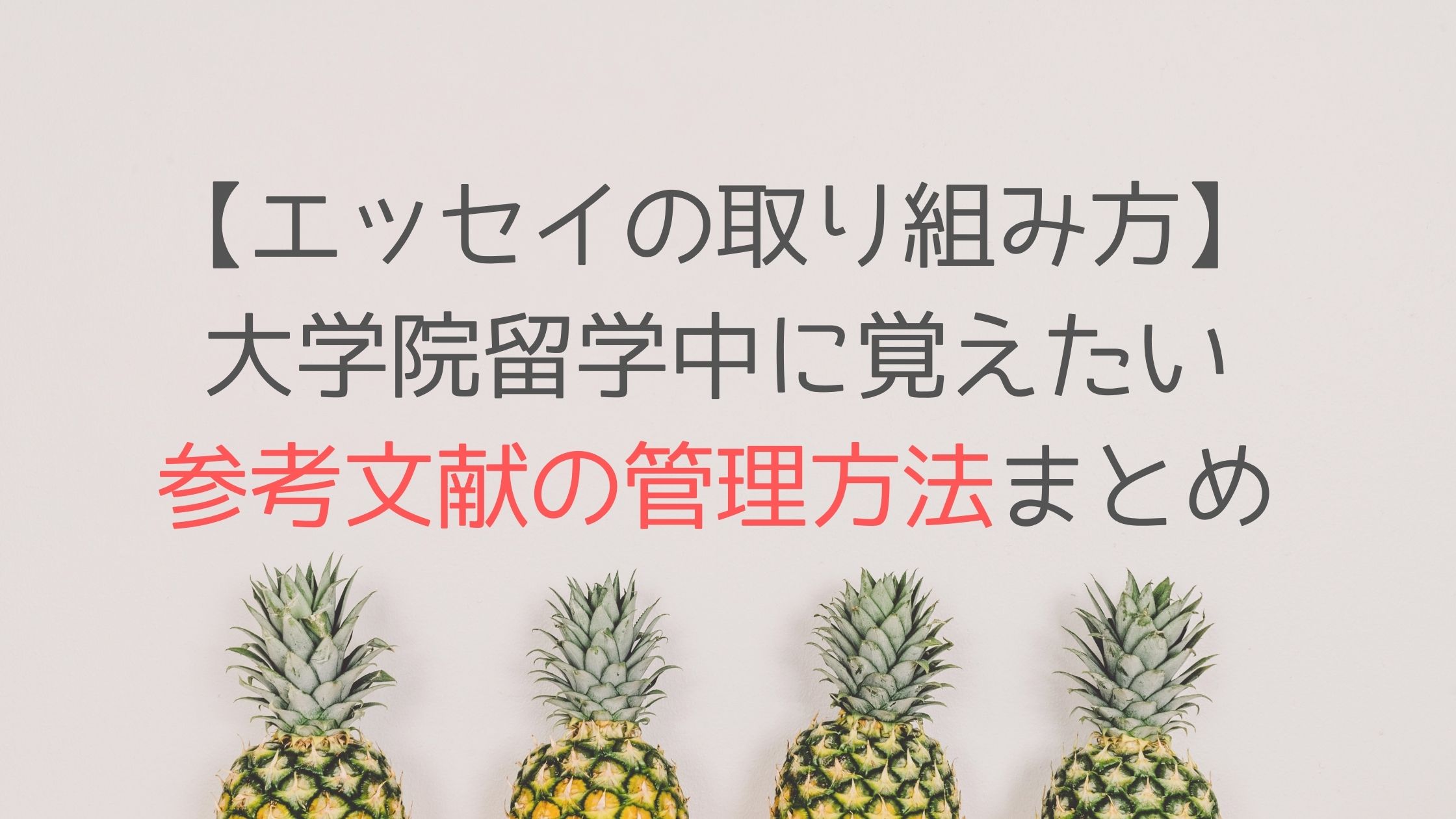

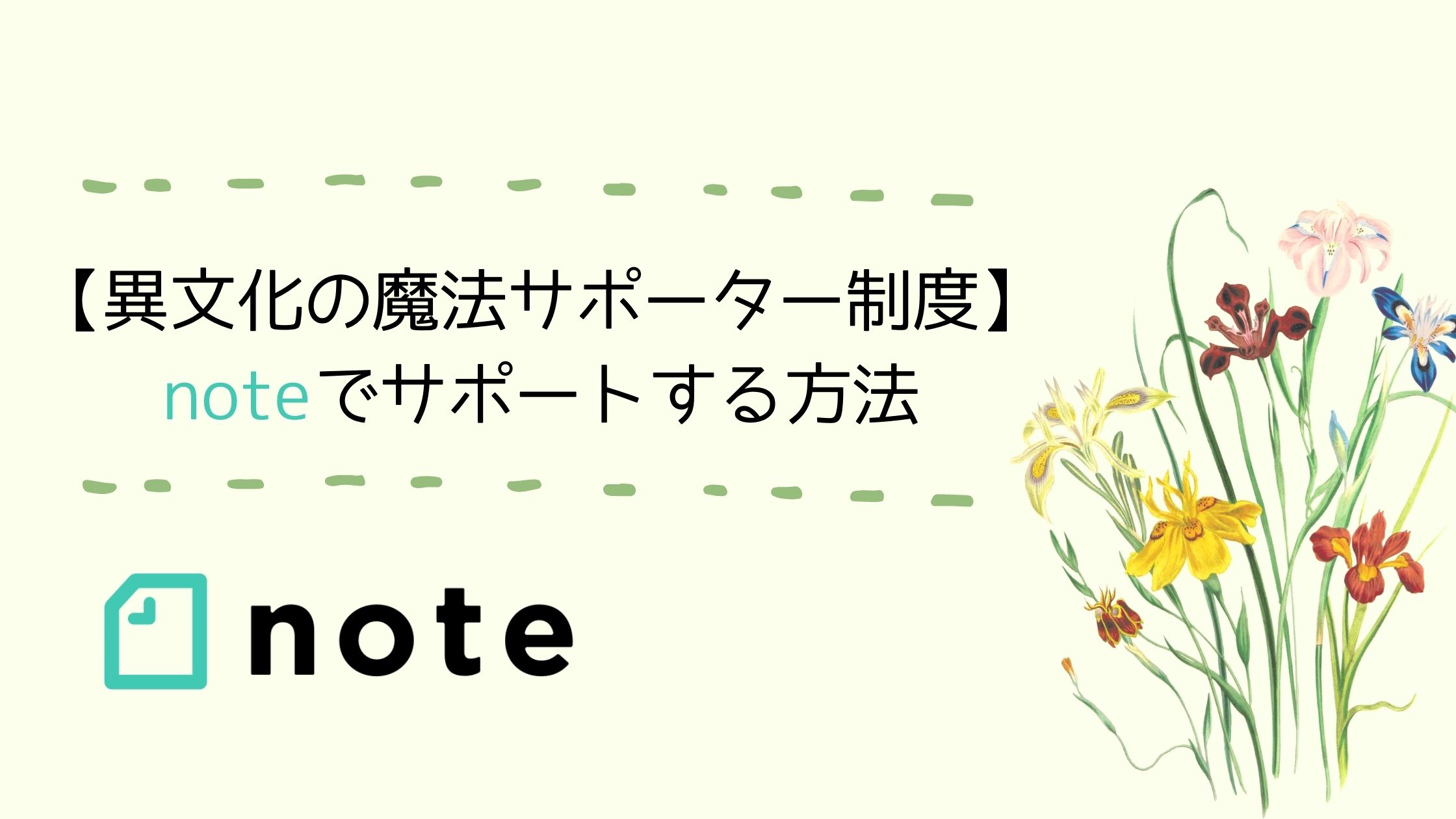
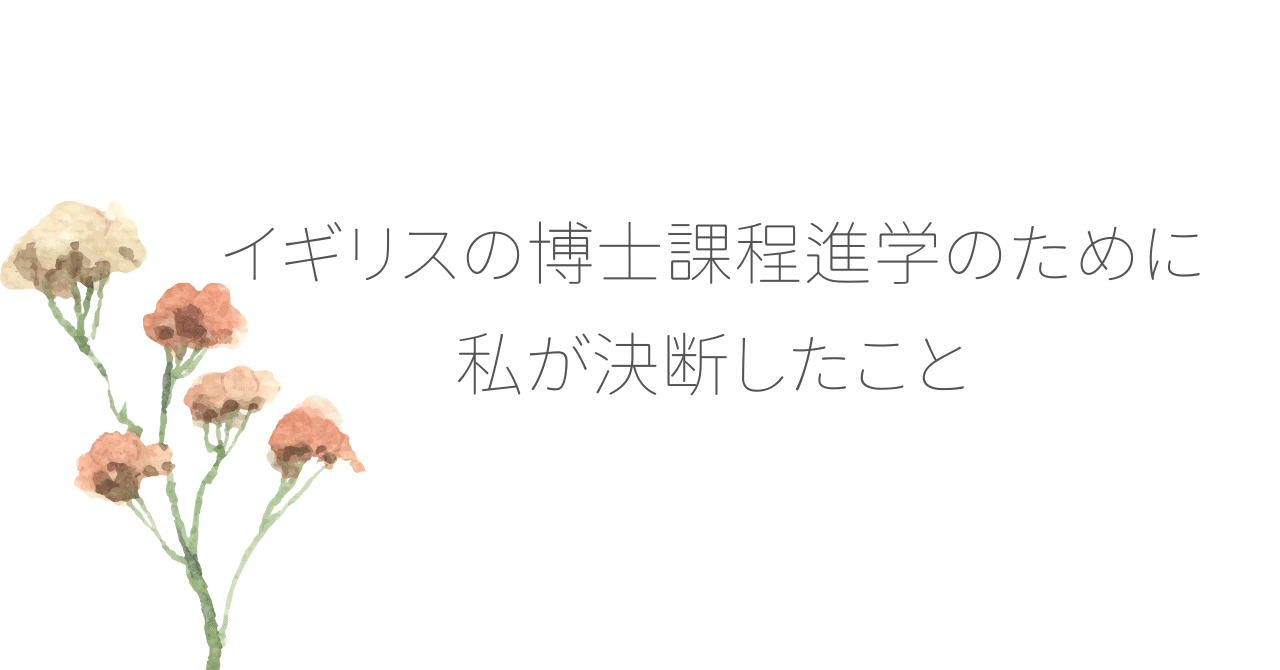
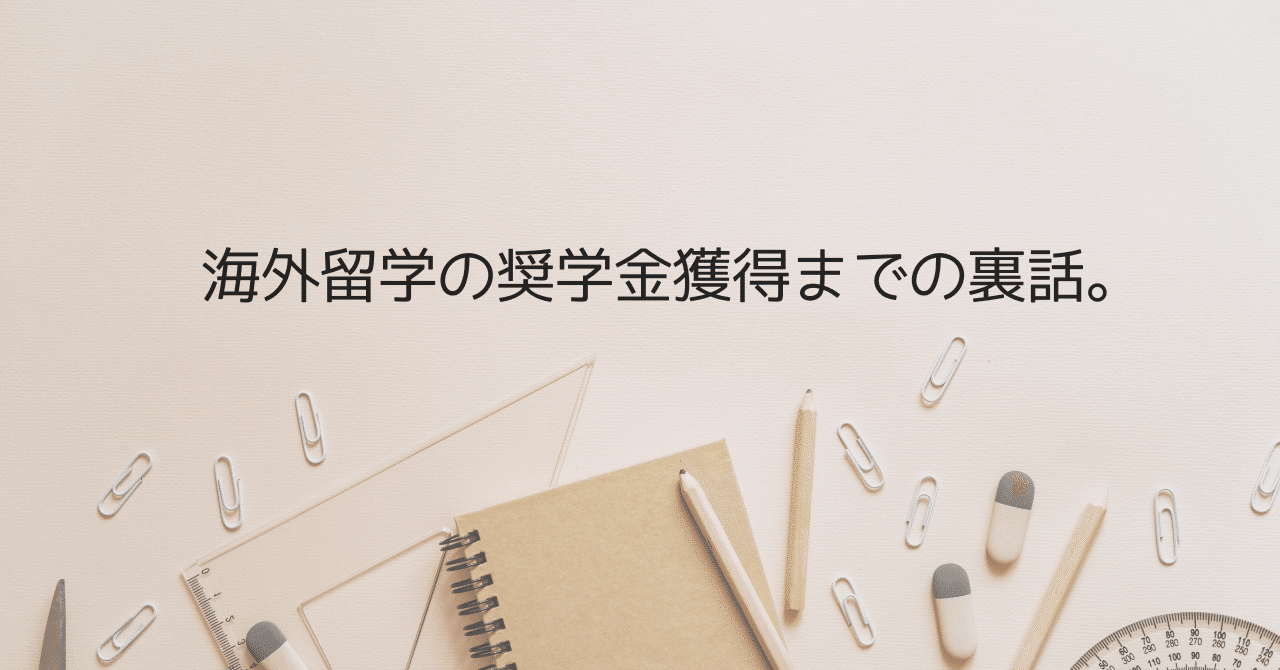



コメント