こんにちは、Sayaです。
今回は日本の大学と共同学会の企画・運営を担当した感想をまとめたいと思います。
学会の詳細は、ネットを調べれば出てくると思うので、それについてはここでは書くつもりはなく、この記事では私自身の振り返りをしたいと思います。
日本の大学と共同学会を開催することを目指して
過去に、私はこんな記事を書いていたんですね。
今回の記事を執筆するにあたって、久々に自分の記事を読んでみたら、笑えました。
よくも、こんなに大きな規模の学会が、不思議な感じでスタートしたなぁと。
無謀にも程がある・・というか・・・。
そして、記事の最後にはこんなことが書かれています。
この先には先生がずーっと仰っている「共同学会開催」というものが待ち受けています。
私の内心は、本当にできるのか・・・??
と、ずっと疑問に思っているんですが、たぶん実現します。
だって、この日本出張も実現したんですもの。
しかも、先生がメールで送ってきた2人の先生の所属先の大学訪問まで実現することになったんですもの・・・。
おそらく、私は博士号取得するまで、ずっとこのプロジェクトに関わりつづけると思います。
もし・・・いつか・・・
UCLのHPに「日本のXXX大学とUCL IOEで共同学会開催、参加者募集!」というかっこいい広告が載ったら、「異文化の魔法のSayaさんだ!」と思っていただけると幸いです。
そして、共同学会開催というかっこいいタイトルの裏は、こんな状況からスタートしているということが、この記事を振り返ると知れることでしょう。
未来ってどうなるか分からないから、面白いものです。
ということで・・・

その「いつか」が来ました!叶ったよー!昔の私ー!
このプロジェクトは2023年10月から始動していたんですね。
この夢が叶ったのは、2025年5月20日ー23日。
たった4日の学会開催のために、準備には約1年半費やしました。
私はこの1年半、この学会の存在が私の頭の片隅にずーっとあって、スッキリしないというか・・・常にモヤモヤしているような状況だったわけです。
今回の学会開催にはいくつものハードルがありました。そりゃ当然ですよね。コネなし、カネなしでスタートしたものですから。
そして、先生が私をプロジェクト遂行のパートナーとして選んだ時点で、人選ミスが甚だしいとも思っていました。
もっとさ・・・、業績のある、コネのある、研究費をしっかり取れる人?とか、他にもいるはずなのに・・・、私みたいな、無名の学生なんかとやろうとするなんて・・・。と、思う日も・・。
でも、これは先生の私に対する信頼の証だったんだと思います。
指導教官と私の関係
私はイギリスに来て5年目になります。
そして、私と私の指導教官との関係も、いつの間にかこんなに長くなってしまいました。
正直、私は特別優秀な学生でもなければ、大学で目立つような学生でもなく、常に自分の能力不足を感じ、悔しい気持ちをずっと抱えています。
でも、私の指導教官は私を常に応援してくれ、私を信じ、私に挑戦の場や活躍の場を作ってくれる人でした。
振り返ると、私は先生がチャンスをくださるたびに、必ず成果を出さなければと必死でした。
私はネイティブのように言語的に優位に立てることはできないけれど、私にしかできないこと、私が少しでも貢献できるところはなんだろうと、常に考え、それを実践するようにしてきました。
それが、こうして学会の形になったと思うと感無量です。
学会期間中、先生からメッセージが届きました。
「この学会は、Sayaがいなければ達成できなかった。本当にありがとう」と。
私の博士課程の奨学金の申請書に込めた思い
この記事を書くにあたって、過去の博士課程進学用の奨学金の申請書のファイルを見てみました。
そこには、世界と日本との架け橋になりたいというような思いが強く綴られていました。
申請書を書いているあの頃は、コネもなく、どうやって達成できるのか?という道筋もはっきりと見えていない、夢物語みたいなことを本気で考え、その時点で考えられること全てをぶつけていました。
今、私が自分の軌跡を振り返ると、私が博士課程で先生と一緒に成し遂げてきたことは、奨学金の申請書に書いた内容を一部現実にしたもののような気がします。
この経験を通して、改めて思うことは、宣言すること(または、自分に誓うこと)は、大事だなということです。
私がUCLに来れているのも、約10年前に、タイのアジアティークで

私はUCLのInstitute of Educationに行きたいって思ったから、そこを目指そうと思う!!
という意味不明な宣言をしたからだと思うんです。
そして、友人に「そんなことできるの?」と言われ、「わかんないけど、たぶんできる!」と言い、二人で笑った覚えがあるんです。
確かに、この道は甘くはなく、思ったより時間とお金をたくさん費やしてしまいました。(今振り返ってみると、なんとも大胆で、面白いことを言ったものだと思います)
でも、自分に誓うことって大事だなって思います。
この先・・・
博士課程を振り返ると、研究をスタートしてからデータ収集が終わるまでの2年間は、博士論文執筆に十分なデータが集まるかどうかで、常にモヤモヤ感と、大きな不安がありました。
やっとデータ収集が終わって安心できると思ったら、次はこの学会の案件が降りてきて、それを1年半抱えていたわけです。
こんな博士課程だったので、これらから解放された今、少しバーンアウトしてしまった感じがします。今日はとりわけそんな感覚があって、ちょっと、研究から離れ、久々に異文化の魔法に自分の気持ちを綴ってみました。
やっぱり、こうしてブログを書いていると気持ちもスッキリしてきて、異文化の魔法は私にとっての楽しみなんだなって改めて思ったりもします。このブログ活動は2019年から続けているものなので、もう6年目ですもんね。好きじゃなきゃ続けられない年数ですから笑
さて、この先ですが・・・
「日本との共同学会をやろう!」という突拍子も無いアイディアが実現した今、これで終わりにならないんです・・・
その目標がゴールとして始まった道のりだったのですが、先生はスタート地点に立ったと言わんばかりに、勢いが増しています。
いつの間にか、これまでの一連のイベントは「ジャパン・プロジェクト」という名前になり、次々と今後の計画が打ち出されてきています。
私はその勢いに圧倒されつつも、ついて行く・・・というか、私がいなきゃ成り立たないものばかりなので・・・。
ひとまず次は、日本から中学生の訪問団が来るイベントがあるので、研究の合間を縫って、準備をしているという感じです。
今後、どんなことが起こるのか私もよくわかりませんが、一生懸命やるのみかな・・・と思っています。

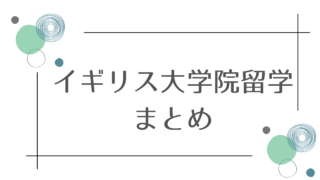
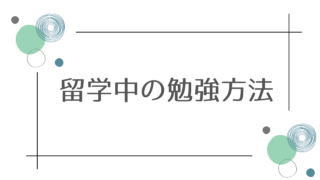
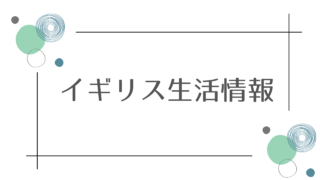
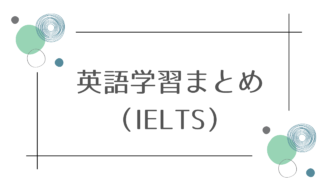
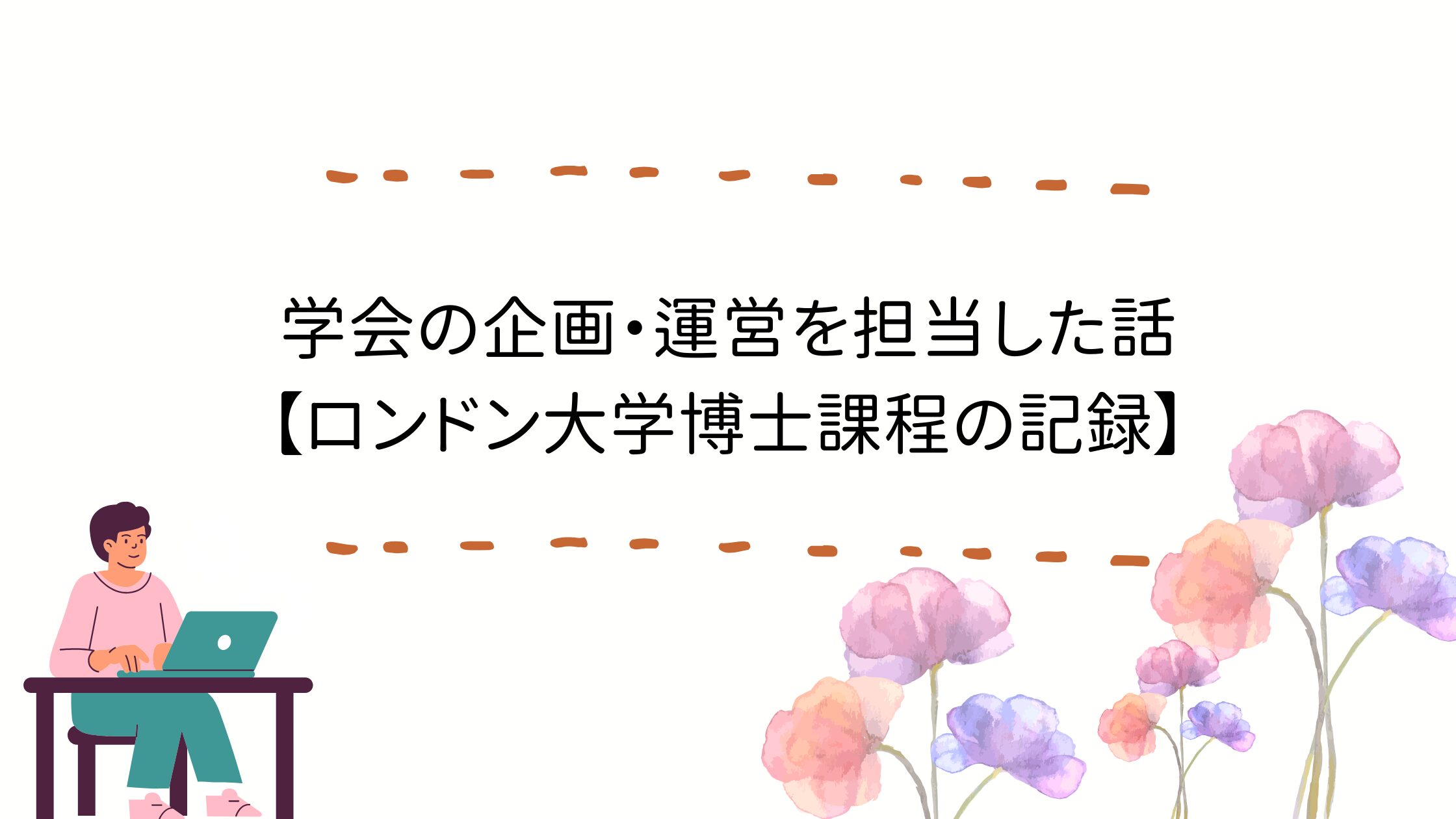



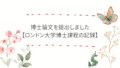
コメント