今回は「教育超大国インド 世界一の受験戦争が世界一の経済成長を作る」(著:松本陽 / 西岡壱誠)のブックレビューです。
実はこちらの本の著者である松本陽さんは、ロンドン大学(Institute of Education)の修士課程の頃の同期でして、よく一緒にご飯を食べに行ったりしていました。
松本さんは、異文化の魔法のインタビュー記事にも貢献してくださったことがあり、私の知らない世界をたくさん教えてくださいました。
久々に松本さんの記事を読んでみたのですが、とても感慨深い気持ちになりました。
あの頃の松本さんの思いが、インドでの起業の道につながり、今こうして本の出版に至ったと思うと、芯の強さと教育にかける情熱を感じて、とても熱い思いが込み上げてきます。
ぜひ、こちらの本とともに、私のブックレビューをお楽しみいただければと思います。
Sayaのブックレビュー
ここからは、私のブックレビューとなります。
まだ読まれていない方のためにも、あまりネタバレになるような書評は書きたくないなと思いつつも、松本さんが本で書かれていたことも含めて、私が感じたことを素直にまとめていきたいなと思います。
(だいぶ話が脱線する部分もあるので、その点はご愛嬌で!)
インドの意外性を知れるストーリー展開
私はこちらの本を購入させていただいたその日の夜に読んだんですね。
寝る前に少し読もうと思い、半分くらい読んで、また明日にしようと思って本を広げたのですが
びっくり仰天。
「え!?インドってこんな感じなの?!」と思うくらい私のイメージとかけ離れたインドの姿が描かれていて、ストーリー展開が気になりすぎ、あっという間に読破してしまいました。
とても読みやすい話の展開で、まるで旅行記を読んでいるような感覚でした。
もちろん、インドの教育事情や経済発展の著しさには目を疑うほどでした。
松本さん自身がインドのことを「まるでシンガポールにいるかのような」と表現していらっしゃったり、「ゴミがない」という表現があったりするのを読んで、私としては「ひょえー」という驚きが隠せませんでした。
それと同時に、自分が持っている国に対するステレオタイプは怖いなと思ったりもしました。
ただ、松本さんの記述はとても丁寧で、インドの多様性や、今回の本で書いている経験について、「あくまでも自分が見たインドであって、インドを一般化しているものではない」ということをしっかりと書いてくださっていて、そういった点も納得のいく記述でした。
つまり、インドには私がステレオタイプで思っているようなインドの姿もきっと存在しているでしょうし、この本で描写されていた松本さんが見たインドの姿もインドであるでしょう。
むしろ、松本さんの見たインドの姿を、このような形で知れたという点で、私のインドに対する見え方もとても変わって、非常に学びの多い内容でした。
インドの未来にワクワク!
本を読んでいると、松本さんのインドに対する情熱がひしひしと伝わってきて、インドって面白い!そして、可能性に満ち溢れている!って思えることがいっぱいでした。
何より、人口のパワーってすごいなぁって改めて実感しました。
現在のインドの人口って14億なんですって。
しかも14歳以下の子どもが全人口の25%も占めていて、大学が足りなく、毎年のように新しい大学が建設されているという実態が書いてあって、本を読みながら、「うわー」と、声が出てしまいました。
最近の日本のニュースは、少子化の影響により大学の定員割れ、学生募集停止、挙げ句の果てには、閉学・・・。なんだか暗いニュースばかりだったので、インドの勢いには圧倒されました。
でも、高等教育のこのような問題は、イギリスでも同じように起こっています。
イギリスの大学は、留学生依存型の経営ですから、留学生が減れば一気に経営が成り立たなくなってしまいます。それゆえに、人気の少ないコースは廃止となり、先生方が失職するといった状況があったりします。
そんな状況を目の当たりにしているので、自国民が14億の規模となると、大学を建設しても建設しても需要があるという状況なのかーと思い、人口のパワーに可能性を感じました。
そして、やっぱりそういった競争の中で高等教育に進む人々ですから、優秀なのは間違いないですよね。
そういった人々が国を作っていると思うと、この先のインドは可能性をたくさん秘めているなと感じました。
教育とは何のためのものなのか?誰のためのものなのか?
ここまでは、私が松本さんの本を読み、純粋にインドおもしろーい!と思った感想だったわけですが、これからは、もう少し踏み込んだ点について、述べていきたいと思います(少し脱線するかもですが!)
著書では、インドの受験戦争の様子について深い記述と考察がなされていました。
受験戦争の勝者はエリート大学に進み、将来は約束されているような実態でした。
それはそれで、とても勢いのあるインドの教育の実態を物語っていて圧倒される文脈でもありました。
でも、その時に私の中で思い浮かぶのは「教育とは何のためのものなのか?」「誰のためのものなのか?」という問いでした。
日本の受験戦争もとても厳しく、進学校の生徒は必死に勉強に向かい、少しでも偏差値の良い大学に進学を希望したいと思っていることでしょう。
自分の過去を振り返っても高校時代は、きつかったなと思います。
ただ、ペーパーテストで高得点を取り、偏差値が高い大学に進学することだけが、教育の目的なのでしょうか?
そんなジレンマを私は教員をやっている頃からずっと抱えています。
インドの受験戦争の実態について知れば知るほど、教育が格差を作り上げている構造が思い浮かんできました。
まるでシンガポールのような一面を持つインド。
日本では考えられないくらいの富を築きあげているインド人。
その富を使って教育に投資しているインド人家庭。
その一方で、私のイメージ通りの貧困に悩む低カーストの人々。
教育や受験戦争という背後に、資本主義社会の構図と後進国の現実を目の当たりにさせられた気がしました。
教育とは何のためのものでしょうか?
誰のためのものなのでしょうか?
教育とは国の発展のための、人材育成のためのものなのでしょうか?
教育とは能力のある人材を選抜する装置なのでしょうか?
スリランカとタイでの思い出
どんどん脱線して申し訳ないのですが、本を読みながら思い返されたことがあります。
それは私がスリランカに住んでいた頃とタイに住んでいた頃の思い出です。
以下、少し私の思い出話にお付き合いください。
スリランカ
スリランカには1年間留学していたことがあります。
その当時知ったのは、スリランカ人はとにかくインドのことを尊敬しています。
インドはスリランカ人にとって、留学したい国の上位ランキングにランクインすると思います。
そんなスリランカにもカーストは存在しています。カーストを超える結婚は非常に難しいです。
そして、スリランカの受験戦争も非常に厳しく、その点でも、インドと同じだと思います。
小学校卒業段階で、全国一斉テストがあり、これの上位層に入ると奨学金付きのエリート養成学校に入学することができ、中学校からエリート教育を受け、大学進学を目指すことになります。
実はある時、友人の実家を訪問したのですが、その家庭には受験生の高校生がいて、土壁剥き出しの小さな部屋で受験勉強をしていました。
受験勉強に使える道具は、紙と鉛筆だけで、あとは、学校でもらえるちょっとしたプリント教材程度だったわけです。
そんな彼は、数学の公式を紙いっぱいに書いて部屋中に紙を貼り付けていました。
それを見た時に、「これは大変だ・・・」と思い、自分の大学受験が大変だったと言っているのとは全くレベルが違うなって思いました。
リソースが少ない中、人生をかけて、一族の望みを背負い、受験に向かっている彼からは、強い覚悟を感じました。
タイ
タイには4年仕事の関係で住んでいました。
その時に出会ったタイ人の女性がいます。
その方は弁護士で、とても優秀な方でした。
現在タイは中進国と呼ばれるほどの経済発展をとげ、とても住みやすい国となっています。
スリランカやインドのようなカースト制度はないものの、社会階級による分断というのは存在しているように見えます。
その中で、ミドルクラスの子ども達に対する教育への期待はとても大きく、子どもの未来の選択肢に対する自由度は極端に少ないようにも思いました。
というのも、教育において、理想とする道は「理系」が基本で、子ども達は医師やエンジニアへの進路を目指すように諭されます。もし理系が難しいようであれば、文系に進み、弁護士になることが期待されるわけです。
学校は基本的に中高一貫で、中学校受験をして学校に入るわけなのですが、クラス分けは成績順です。
1組がトップクラスで、理系になっていることがほとんどです。
そんな具合ですから、私が出会ったタイ人の女性も父親の期待にこたえるように必死に理系のクラスで勉強をしつづけていました。
しかし、大学受験の際に理系進学を諦め、文転し父親と同じ弁護士の道を進んだわけなんです。
といえど、勉強への動機づけが、家族の期待であったため、弁護士に向かない自分と、本当に自分がやりたいことは何なのか?という葛藤をし続けていたそうです。
私がなぜ、松本さんの本を読み、スリランカとタイの思い出が、思い浮かんできたのか?というと、「教育とは何のためにあるのか?」ということをすごく思わされる本だったからなんです。
スリランカ、タイ、インドの社会状況や経済状況を考えると、学歴を手にいれることは一定の社会的地位を手にいれることにつながり、それは、社会的地位を上昇させるための大きなチャンスなわけです。
ときには、貧困から抜け出す一つの方法だったりします。
または、家族がその社会的地位を守り続けるための方法だったりするわけです。
私は、とあるタイ人にこんなことを言われました。
「子ども未来はある程度固定しなければいけない。やりたいことを本人の意思で自由にさせるなんて絶対にダメだ。タイでは一度社会的地位を失ったら、もう二度とその地位には戻れなくなるから。一族の未来に関わることなんだ。」と。
その時に、私が思っている教育の姿は、日本が比較的平和で、恵まれている国であるからこその思想なのかなと。平和ぼけしてしまっているのかなと思ったりしたんです。
日本とインドの教育の未来
インドの教育事情を知れば知るほど、タイやスリランカで見た経験と交差する点が多く、色々と考えさせられました。
それとともに、このように勢いのあるインドのような国がどんどんと優秀な人材を輩出し、海外企業がこぞって、その人材獲得に乗り出ている現実を知ると、これからの日本の教育はどのような方向に向かっていく必要があるのかな?とも思ったわけです。
日本の教育現場は、教員の成り手が少なかったり、私の友人たちの中には、業務量の多さに疲弊して、もう辞めたいと思っている子も多かったりします。
最近は、そういった日本の教育現場の残念な点ばかりが目について、海外はもっと勢いがあるのに、日本は・・・と批判されやすい状況になっている気もします。
ですが、私は日本の教育には、海外に劣らない強みがたくさんあると思っています。
松本さんも著書で仰っていたように、日本人の識字率の高さは素晴らしいと思います。
また、日本の学校で取り入れている朝読書の時間はとても大事な習慣形成だと思うんです。
それから、日本の先生方は子ども達の「心」を大切にしようとする姿勢が本当に素晴らしいなとも思っているわけなんですね。
私は理想主義者かもしれませんが、教育の目的は「経済発展」「人材育成」も大事だと思うのですが、「個人が自由で幸福に生きるため」という視点も持ちたいと思っているんです。
だからこそ、私はインドのような過度な受験戦争はどの程度の人を幸福に導いているのかという点に疑問を持ってしまいます。
そして、こういった受験教育の行末は、ある程度経済発展を仕切った国家の先に何が待ち構えているのだろうとも思うわけです。
日本の経済は高度経済成長期で経済発展が止まり、今の東南アジアや南アジアのような勢いのある経済状況を経験したことがない若者が増えています。
では、日本は今後どうなるのでしょうか?
私は日本の未来を考える時「自分だけ(または自分につながる人々だけ)がよければいい」という視点ではなく「自分が社会の一員として社会を共に作っていくんだ」という視点を持つことが大事なのかなとも思ったりするのです。
きっと、そういった視点が、新規的で、画期的で、革新的な、一歩先の明るい日本社会につながるのかなと思ったりするわけです。
その素地を作り上げるのがこれからの教育の役割なのかと思っています。
おわりに
ブックレビューを書くと言っておきながら、自分の思い出話が多くなってしまったのですが・・・
松本さんの著書を拝読したことをきっかけに、私の思考があっちこっち広がりすぎて、一人で世界旅行をした気分になりました!
内容も刺激的でしたし、松本さんの人生そのものも刺激的でした。
私もがんばろう!って勇気をもらえる一冊でした。
私のブックレビューを読んでくださった方は、ぜひ松本さんの本に目を通してみてください。

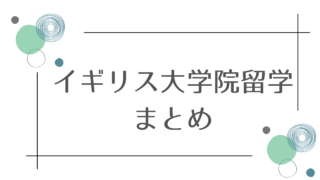
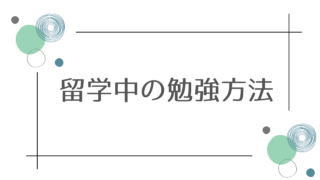
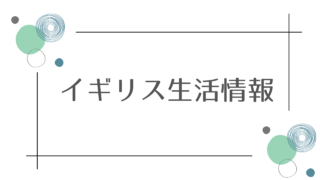
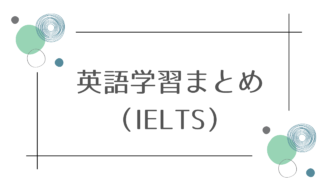
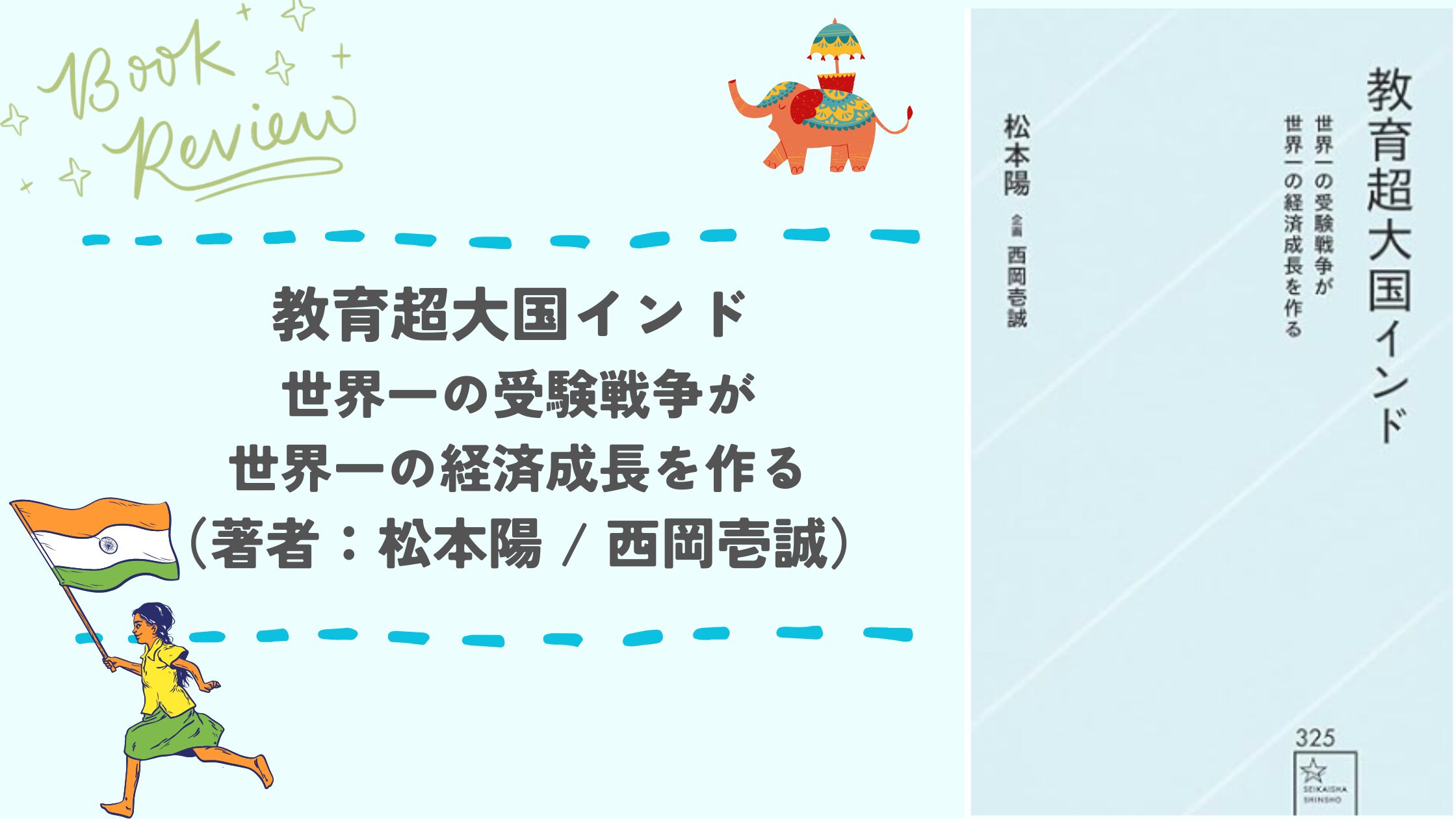

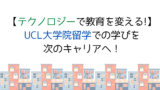

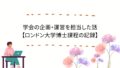
コメント